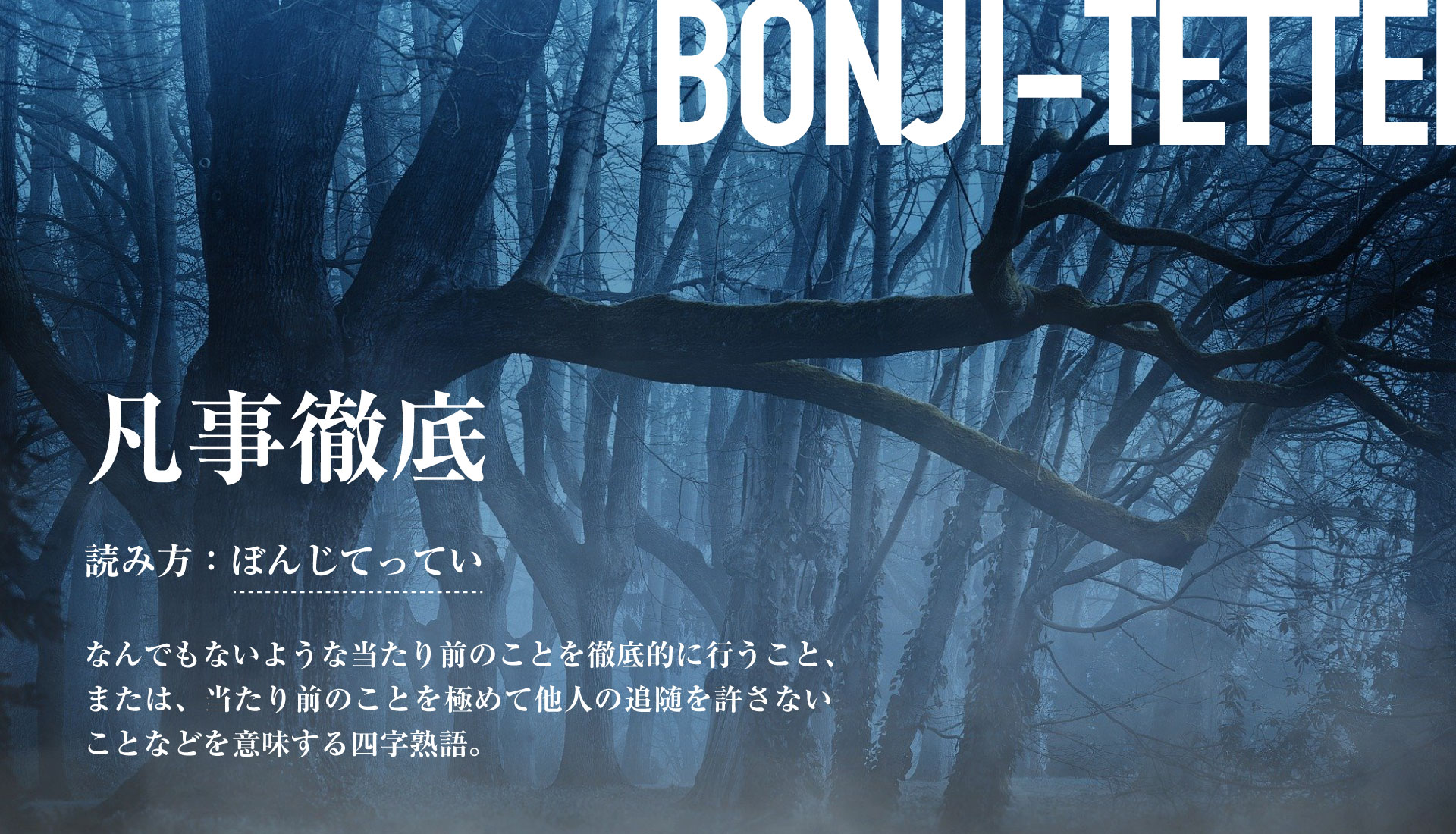中小企業の事業支援と最近読んだ「ビジョナリーカンパニーZERO」の共通点から見出す戦術における「凡事徹底」の大切さ。
今回は何もデータはなく、私が日々働く中で感じた所管をまとめています。
中小企業の成長戦略
普段デザインのみではなく、デジタルマーケティングだったりと事業の売上に関する仕事も行っている中で感じたことです。
中小企業は大企業のようにリソースが潤沢にある訳でもございません。限られたリソースの中でどうやって成長していくのか。悩ましいものであり、多くの企業が抱える課題でもあります。
その中で事業者たちは自分達らしい事業とは何かを真摯に考え、日々の活動に取り組んでいく。制限があるのは承知で、自社の強みを活かした事業展開を行うのです。
そうした過酷な環境の中で中小企業の事業の成長にはどんな要素が必要なのか、それは卓越したデザインでしょうか。卓越したマーケティング施策でしょうか。リソースが限られている中小企業に必要だと感じるのはただ愚直に適切な取り組みを積み重ねる「凡事徹底」です。
施策を適切な時期に、適切な予算感で行う
中小企業の成長に派手な取り組みは必要ないとつくづく思います。
例えば立ち上げのタイミングだとプレスリリースを打ったり展示会に出したりと立ち上げ期ならではの適切な取り組みがあると思います。
数年経ったブランドだとリピート施策に取り組むのも一手でしょう。
季節で売上が変わる商材であればしっかりと売上のピーク期を予測して逆算した上で施策を構築していく必要があるでしょう。とても簡単なのですが、ただこれを行うのがどれだけ難しいか。日々中小企業の方々と向き合っていると感じます。
さらに大切なことはタイミングだけでなく予算。
好機を逃さない為にも勝負をかけるところなのか。
もしくはここでは予算をかけるべきでないと判断し予算を抑えるのか。
もちろん正解はございませんが、経営者のセンスを感じる場面でもあります。
実際にどんな規模の会社でもやりとりをしている中でセンスを感じることが多々あります。
それは自分達の勝負どころと予算感を感覚的に理解している時です。自社の事業の強みと外的な立ち位置を考え、提案されたことに対して瞬時に納得性のある判断をする。タイミングとリソースを判断し、そこで決めた取り組みを徹底することで中小企業の売上はしっかりと伸びていくのだなと日々感じております。
必要なことは派手な戦略ではなく、日々の戦術。設計だけでなく実装していく姿勢でしか目の前の事業は成長しません。
戦術の偉大さをビジョナリーカンパニーから学ぶ
そんなことを薄らと感じながら書店に行き、たまたま目に入った「ビジョナリーカンパニーZERO」。タイミングだと感じ目を通してみました。
ビジョン経営をベースに書かれている本だと思っていたので(実際にはベースはビジョンを経営の主軸に置くことを推奨している)、具体的なアクションが出てくることが意外でした。
意外だったのは本書の最終章に「戦術」が置かれ、これまで話してきた比較的抽象度が高い話をどうアクションにつなげていくことが必要かといったことが記されていたことです。
細かいタスクの進捗管理の方法から、働き手のマインドセットをどう変容させていくのか。
実際に本書を読み進めていくと話が抽象から具体、もしくは大枠のものが細分化されていくような感覚に陥るのですが、どれだけ大枠で物事考えても、結局は日々の行動に繋げない限り効果はないわけです。そういった細部の大切さを、よもやビジョナリーカンパニーという本から学びました。ここで改めて「凡事徹底」の大切さを感じました。
机上の空論にならないように、実践することの大切さと難しさ
ここからは私の日々取り組んでいることをベースに具体の話に戻ろうかと思います。
上記のように戦略だけではなく、戦術が大切だと主張し、さらにそれらは特段派手な取り組みでなくとも誰でもできることを誰よりも行う、いわゆる「凡事徹底」だと指摘しました。
その中でこれから踏み込んだ話をする前に改めて戦略と戦術の関係を整理しようかと思います。
戦略とは一般的には下記のように説明されます。
———–
① いくさのはかりごと。 特に、戦いに勝つための大局的な方法や策略。 戦術より上位の概念。 ② ある目的を達成するために大局的に事を運ぶ方策。
———–
戦術とは一般的には下記のように説明されます。
———–
作戦または戦闘の直接目標を、最も効果的に獲得することをねらいとして行われる方法的技術。
———–
つまり戦略は大局を見て方向を示し、戦術によって実行する。そういった関係性です。
これまで凡事徹底が必要だと主張してきましたが、それは最終的に成長できるかがそこに懸かっているという話であり、決して戦略は必要ないとは思っておりません。むしろその逆で、戦略が破綻してしまうと以降の取り組みに損失が発生しかねないので、非常に重要な点と言えます。
どこまでもつきまとう「ヒト・モノ・カネ」
ヒト・モノ・カネという言葉を聞いたことはありますでしょうか。もし聞いたことがなくとも、企業経営をされている方であれば嫌というほど日々感じている課題かと思います。
ヒト・モノ・カネとは一般的に辞書には以下のように書かれています。
———–
企業が経営を行う上で利用できる有形あるいは無形の資源。 人的資源・物的資源・資金力・情報・商標・信用などの総体をいう
———–
とされています。つまり、企業経営における有形・無形の資源のことです。
ここで実際に日々感じていることは「ヒト・モノ・カネはその言葉通りの順番で足りていない」ということです。
特に中小企業においては、例えば先代から引き継がれたモノがあるケースが多いです。資金も補助金を利用したりと調整している方々も大勢いらっしゃいます。しかし、ヒトだけは中々うまくいくケースが少ないなと感じます。
これまでの市場が縮小しているのか、OEM1本で事業を行うことに違和感を覚えたのか。様々な理由で新規事業の立ち上げや、既存事業の立て直しを測ります。その時に現状の人的リソースで賄えるケースはほとんどないと感じます。
「たった1人でもいいからこの事業にベタ付きでついて働いてほしい」、事業を勢いよく伸ばすにはそういった考えが出るもの分かります。しかし、こういった状況の企業が1人雇うだけでもかなりのご決断です。雇ったはいいものも、実際それだけ事業に動きがでるのか、タスクを生み出せれるのか。いろんな悩みがあるかと思います。
しかし、人を入れるのが遅れ、モノが生まれず、それによってカネが集まらない。そんな悪循環になることも現実の課題としてございます。
そこで重要視されるのが「戦略」です。もちろん、雇った方が狙った通りの働きをしてくれるならそれに越したことはございませんが、事業の内容的にそうではなくなっても別案としてこれを動かしてもらおう。もしくはこの事業はこういう方向性で、ここに絞ってやるぞ、等々。戦略を決めることによって日々の戦術が矯正され、無駄な取り組みを行わなくて済みます。とはいってもこの戦略を考えるのが一つの大きなハードルになるかもしれませんが、限りあるリソースを無駄なく使うには戦略の立案は欠かせません。
その上で戦術です。個人的には戦略は大はずしさえしていなければそれでいいくらいだと思っています。戦略だけで何かを成し遂げれることはないからです。
だからこそ素早く戦略を決め、日々の誰でもできる取り組みを誰よりもやる。
ただ唯一そこに目を向け、着々と成長していくことが必要だと感じます。