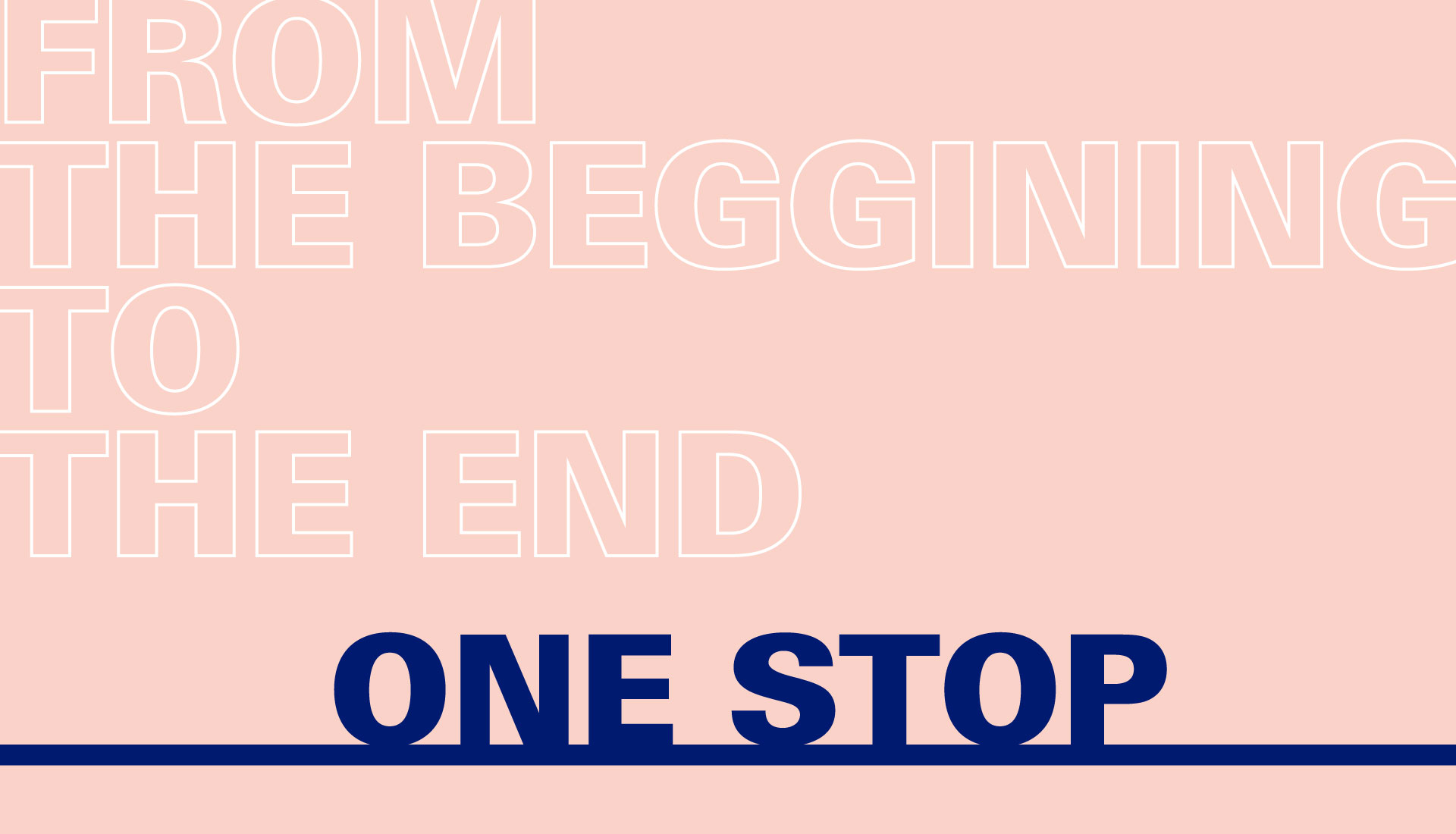NY-Dではシンプルなデザイン制作ももちろんお受けすることもあります。しかし、これまでの仕事を振り返ると、戦術段階からご一緒したケースの方が成果を出しやすいなと感じます。ここに強みや、ご提供できる価値に繋がるかと思いますので少し掘り下げてみようかと思います。これまではB2Cのブランドのご支援をさせていただくことが多かったのでそういった例を元に話を展開していきます。
戦術を考えることの重要性
まずは戦術を考えることの重要性。
戦術は今から行う施策をどういう方向性や手法で行うのかを考える段階です。戦術が曖昧のまま進めてしまうと施策をリリースしてからの結果のイメージもできず、振り返りもできないので今後の知見として活かすことができません。こういったユーザーの目に触れない箇所は、見過ごされがちですが非常に大切にしている点です。
もちろんこの戦術は簡単に決めることはできません。一般的な市場リサーチ(競合他社の手法や価格帯、施策を行う一般的な時期、キーワードの設計等々)だけでなく、何より大切にしたいのは事業者の方ご自身が「誰に手に取ってもらいたいか。」です。
現在の世間の状態だとこういう売り方が一番売りやすいけれど、事業者の達成したい事を考えると違う手法で施策に取り組みたい。
その塩梅の中で必死に考え、市場と事業者の双方が納得する形を探ります。
そうして時間をかけ、想いを共有しながら考え出した戦術をデザインに落とし込んでいきます。
デザインへの落とし込み
どれだけ時間をかけ、必死に考えた戦術でもユーザーの目に止まるか、記憶に残るかで評価が決まってしまう部分もございます。
それを最大限いい形にしたい。その為にデザインを活用します。もちろんデザイナーですので、手段としてだけでなく自分なりの美的感覚を持って表現に臨みます。しかし、制作中でも脳裏にはやはり「必死に考えたこの取り組みをいい形で伝えたい。」そんな想いがよぎります。
だからこそ、ビジュアル表現としても質が高く、戦術の意図に沿ったデザインアウトプットを出せるのではないかと考えています。
両方できるからこその強み
プロジェクトの規模によっては戦術は戦術の担当者、デザインはデザイナーと担当が分かれるでしょうし、それが一般的であるとも思います。
しかし、敢えてそこをひとつの流れとして認識し、取り組む事で戦術面、表現面の両面で本質を見失わず、最後まで軸がブレないままやりきれると思うのです。
もちろん、こんなやり方では大きい仕事は務まりません。しかし、規模がある程度限定されているプロジェクトではこういったワンストップでやりきれることにやりがいや価値を見出すことができます。絞っているからこそできる価値提供、これがNY-Dの強みかと感じました。